こんにちは!
宅建士兼エンジニアのしゅんです!
突然ですが──
「税・その他の分野って、他と比べて優先度低くない?」
「正直ここは捨てても合格できそう…」
そんなふうに思っていませんか?
たしかに、宅建試験の配点バランスを見ると、
- 宅建業法:約20点
- 法令上の制限:約8点
- 民法(権利関係):約14点
- 税・その他:約8点
この中で、
税・その他は後ろに回されがちな
「優先度低めの分野」に見えますよね。
でも、ちょっと待ってください。
合格者の多くが目標にしているのは、
- 宅建業法で満点近く(18〜20点)
- 法令上の制限で8割(6〜7点)
- 民法で6割以上(8〜9点)
合計
…となると、
合格ライン(35~37点)に届くには
税・その他で4〜5点以上取れるか
どうかが分かれ目になるんです。
つまり──
この8点の内半分を全部落とすと、
どれだけ他で点を取っていても
「あと1〜2点届かず不合格…」

ということになりかねないんです…
優先度は「低い」が、
「落としていい」わけではない!
もちろん、
時間が限られている中での勉強戦略としては、
- 宅建業法
- 法令上の制限
- 民法
を優先すべきです。
でも、それは
「税・その他をやらなくていい」
という意味ではありません。
むしろ、
ここで他の受験生が落としている1〜2問を拾える人が、
「ギリギリじゃなく、安心して合格」
できるラインに乗れるんです。
というわけで、今回は税・その他の
不合格にならないための
効率的な勉強方法を解説していこうと思います!
税・その他で狙うべき“得点しやすいテーマ”
税・その他分野は、
実は出題傾向が偏っており、
効率よく対策すれば得点しやすいゾーン
とも言えます
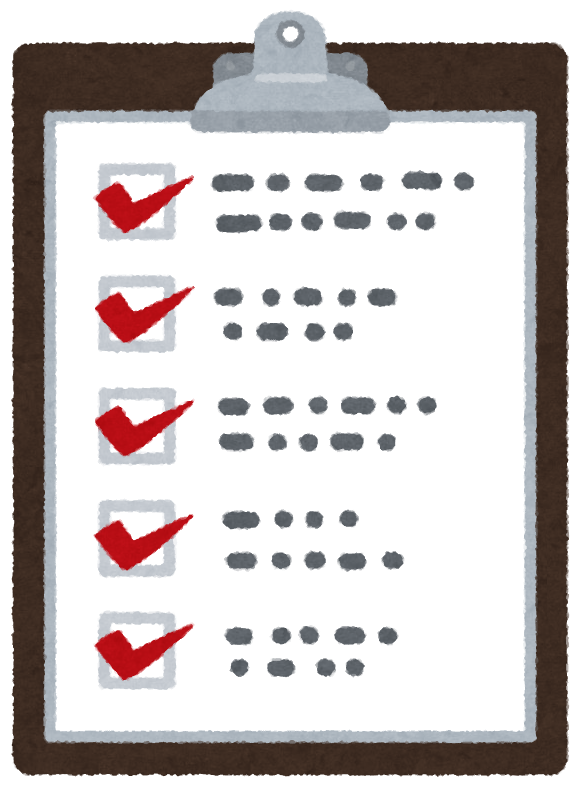
まずは、全体の得点配分を見てみましょう
| 出題テーマ | 出題数(目安) | 出題傾向・補足 |
|---|---|---|
| 固定資産税/不動産取得税(地方税) | 1問 | 年によりいずれか1問出題 |
| 所得税/印紙税/登録免許税/贈与税(国税) | 1問 | 最近は印紙税が主。印紙税がない年は他の国税から出題 |
| 地価公示法/不動産鑑定評価基準 | 1問 | 交互に出題されるケースが多い |
| 住宅金融支援機構法 | 1問 | 毎年安定して1問出題 5点免除対象科目 |
| 不当景品類及び不当表示防止法 | 1問 | 毎年出題される。内容は比較的シンプル 5点免除対象科目 |
| 土地 | 1問 | 土地の種類・用途など 5点免除対象科目 |
| 建物 | 1問 | 建築構造・用途などで1問出題 5点免除対象科目 |
| 統計 | 1問 | 過去の傾向と平均値などを問うデータ型問題。 5点免除対象科目 |
ここからは、
「税・その他」分野の中でも、
どこに力を入れるべきか?
を整理していきます!
絶対に落とせない!確実に取りたい“必須3点”
この3つは、
出題傾向が明確で毎年1問ずつ出題される超重要ゾーン。
初学者でも正答が狙いやすいため、
必ず得点したい3点です。
不動産取得税または固定資産税(地方税)
毎年どちらかが1問。計算問題ではなく、
基本ルールだけで解ける内容が大半。
印紙税または登録免許税(国税)
印紙税が中心に出題されるが、
登録免許税・贈与税が代わりに出る年もあり。
知識整理だけで正解できる設問が多い。
地価公示法
不動産鑑定評価基準かどちらかが出題されるが、
地価公示法が出題された場合
出題形式も一定で得点しやすい。

できれば押さえたい!上乗せ得点ゾーン
このゾーンは、「対策すれば取れる」が、
「時間がなければ後回しもOK」という位置づけです。
住宅金融支援機構法や景品表示法などは出題範囲が限定的で、
過去問演習だけでも高い正答率が見込めます。
また、土地や統計といった5点免除対象科目も、
出題形式がある程度パターン化されているため、
スキマ時間での復習でも十分得点可能。
メイン3点に加えてここでもう2点取れれば、
合格ラインがぐっと近づきます!
所得税(譲渡所得)/贈与税
所得税は複雑なので後回しでOK。
贈与税は頻度低めでも基本知識あれば得点可能
住宅金融支援機構法
毎年1問。出題範囲は少なく、
過去問中心の対策で十分
不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)
毎年1問、内容は基本で対策しやすい。
簡単で常識的な問題が多く、絶対に得点したい
土地
各1問出題。
過去問による消去法でOK
統計
毎年1問。
試験直前に最新データを押さえておけば得点チャンス
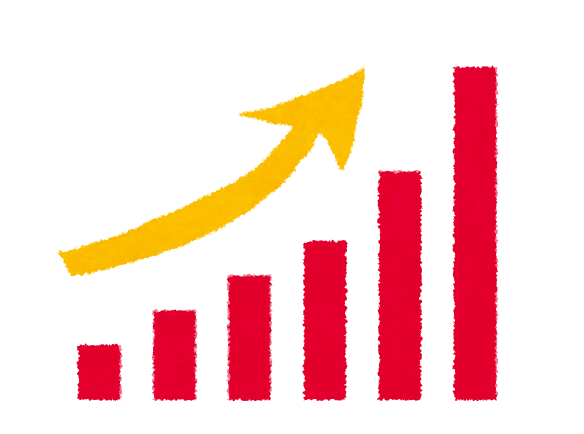
余力があれば勉強しよう!捨て問の2項目
もちろん、
すべての項目に同じ熱量で取り組むのは非効率です。
合格を目指すなら「手を出す順番」も重要です。
特に次の2項目は、出題傾向が不安定で難易度も高め。
余裕があれば対策、という位置づけでOKです。
不動産鑑定評価基準
これは地価公示法と交互に出題されるものの、
その内容は「原価法・収益還元法・取引事例比較法」など
専門性が非常に高いため、得点するのが難しいです
建物
形質・構造・種別などのテーマですが、
出題は年間1問とはいえ、
記憶すべき内容が広く、選択肢の形式も多様
正答率が安定しにくい分野です

得点の効率化をめざす”実践したい3STEP”
STEP1:「まずは3点死守!」得点源ゾーンから固める
まず狙うべきは、
毎年ほぼ必ず出題される3つの定番テーマです。
- 固定資産税/不動産取得税(地方税)
- 印紙税/登録免許税(国税)
- 地価公示法
どれも出題パターンが一定しており、
複雑な計算も少なめ。
過去問を数回繰り返すだけでも、
確実に得点源に変わります!
この3問でしっかり得点できれば、
他の分野のミスもカバー可能!
ここを落とさないことが、
税・その他攻略の出発点です

STEP2:「+2点を狙う」シンプル対策で差をつける
次に狙うのは、
取りやすくて見落とされがちなテーマたち
- 住宅金融支援機構法
- 不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)
- 土地・統計問題
これらは、出題形式がある程度決まっており、
範囲も狭め。
短時間の対策でも得点に直結しやすい
“穴場ゾーン”です!

STEP3:「余裕があれば」難問2テーマに軽く触れる
すべてを網羅するのは非効率。
だからこそ、
捨ててもいいテーマを見極めることも戦略の一つです。
- 不動産鑑定評価基準
- 建物
この2つは出題傾向が読みにくく、内容も専門的。
時間に余裕があるときに
「さらっと確認」程度でOKです。
無理して全部を追わず、
“取るべき問題だけ拾う”
この割り切りが、
合格への近道になります!

まとめ:軽視されがちな「税・その他」で、合格に差がつく!
「優先度は低いから、落としてもOK」──
そんなふうに思われがちな「税・その他」分野ですが…
“ライバルと差がつく”ボーナスゾーン
なんです!
優先して勉強するところさえ
おさえれば――
得点しやすい問題だけ拾って
勝ち逃げできる分野

です!
ライバルが落とすこの1点を
拾えるかが、宅建士合格のカギになるかもしれません!
もちろん、他の重要分野がまだマスター
できていない場合、そちらを優先すべきですが
今からでも、時間があるときに…
- 【過去問チェック】税・その他分野をまとめて3年分解く
- 住宅金融支援機構法や景品表示法を朝の10分で復習
宅建試験は「あと1点」の勝負。
だからこそ、
みんなが後回しにする「税・その他」で拾えるかが、勝負を分ける!
この分野をマスターして、
“安心して合格できる点数力”を身につけましょう!

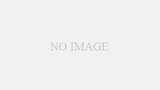
コメント