こんにちは!
宅建士兼エンジニアのしゅんです!
突然ですが、
宅建の「借地借家法」の学習中に、
「定期借家契約とか普通借家契約とか、似てて混乱する…」
「更新?期間?正当事由?…ワケがわからない!」
「法律の条文が多くて、全然理解できない…」
そう感じているあなた。
それ、めちゃくちゃもったいないです。
実はこの「借地借家法」は
ほぼ毎年2問出題されており、
コツさえつかめば得点源に
できる分野なんです!
私自身も、
宅建の勉強を始めた頃は、
「ややこしくてめんどくさそうだな…
後回しにしよ」
なんて思っていました
ですが、実際に過去問などに取り組んでみると、
民法に比べて覚える条文も多くなく、
過去問などでポイントを押さえれば、
ほぼ確実に2点取れる超高コスパな分野でした!

逆に言えば、これを落とすと…
- 民法で苦戦してるのに、借家法でも点が取れない
- 模試や本番で「ああ、これ復習しておけば…」と後悔
- 本来なら届いてた合格点を、たった1点で逃す
そんな未来が現実になってしまうかもしれません。
特に合格できる力がある受験生はこの分野を
落とさない可能性が高いので
絶対に落としたくない分野です
この記事を読めば、こんな未来が待っています。
- 民法と借地借家法、
どちらが適用されるか見極められるようになる! - 過去問でよく出る
“ひっかけパターン”を先回りして対策できる! - 苦手意識のある人でも、
着実に2点を狙える得点源に変わる!
意外と簡単?借地借家法について
そもそも借地借家法とは
借地借家法(しゃくちしゃっかほう)は、
宅建士試験の「権利関係」分野に登場する
法律のひとつです。
これは名前の通り、
土地や建物を借りて使う人(借主)を守るためのルール
がまとめられた法律です。

簡単に言うと、
- 借地=土地を借りる契約(地代を払って土地を使う)
- 借家=建物を借りる契約(家賃を払って建物を使う)
この2つの契約に関して、
「貸す側」と「借りる側」の間で
不公平が起きないように、
公平にバランスを取るための法律が
借地借家法なのです。
借地借家法の目的
この法律が存在する一番の目的は――
借主(住む側)を保護すること。
なぜかというと、
土地や建物を持っている貸主に比べて、
借主の方が立場的に弱くなりがちだからです。
例えば、今まで住んでいたマンションの大家から
「この部屋を物置として使いたいから、
明日出て行ってね」とか
「なんとなく気に入らないから、
次の更新で契約終了ね」
なんて言われたら困りますよね?

こういったケースを防ぎ、
「借主の生活の安定」を守るのが
借地借家法の最大の目的なんです。
宅建試験で問われる借地借家法の具体例
試験で出てくるのは、おもに以下のような内容です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 借地契約の更新 | 期間満了後も自動で更新される?拒否するには正当な理由が必要? |
| 借家契約の更新 | 更新拒絶の通知をする期間は? |
| 定期借地・借家契約 | 契約終了後に更新されない「例外ルール」について問われやすい |
覚えたはずの数字がぐちゃぐちゃに!?「数字迷子」になる落とし穴
借地借家法で
多くの受験生がつまずくポイントのひとつが、
細かすぎる「数字」です。
たとえば──
- 借地権の契約期間は原則「30年以上」
- 借家権は「期間の定めがなくてもOK」
- 定期借家契約なら「1日でも期間を決めれば成立」
- 更新拒絶の通知は「1年前~6ヶ月前までに」
- 借地契約の更新後の期間は「20年 or 30年」?
…など、どれも重要なポイントですが、
とにかく細かい数字が多すぎる!
そして厄介なのが、
「似てるけど少しだけ違う」数字が多いことです。
最初は「ふーん」と覚えたつもりでも、
過去問を解くと…
と、数字の違いに混乱し、
頭の中がごちゃごちゃに
なってしまう人が続出します。
かく言う私も
「あれ?更新拒絶は何ヶ月前だっけ?」
「定期借地の期間って何年以上だった?」
「借家は無期限でも良かったっけ?」
この分野でこのような感じで
ごっちゃになってしまってました…
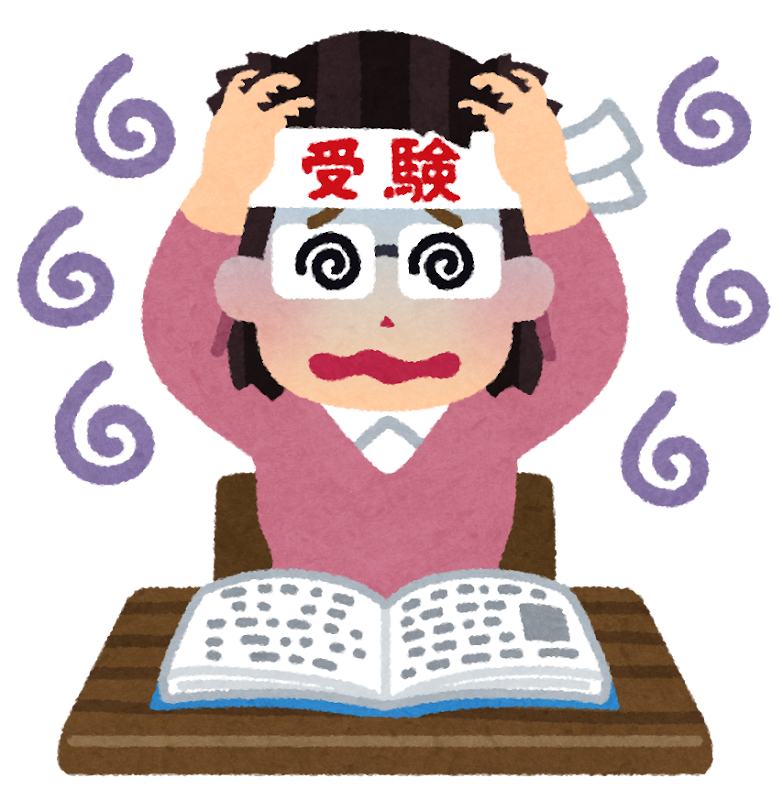
おすすめの覚え方は比較表や語呂合わせ、
図解などを使って一気に整理するのもおすすめです。
借地借家法は数字でつまずかなければ、
実はかなりの得点源。
どっちが出番?「民法」か「借地借家法」かを見分けよう!
宅建試験でよく出るのが、
「この契約には民法が適用されるか?
それとも借地借家法か?」
という見極め問題です。
ここで混乱する原因はズバリ、
民法にも賃貸借契約のルールがあるから。
実は、土地や建物の賃貸借については、
まず基本となるのが「民法」の規定。
ただしそれだと借主が
不利になるケースがあるため、
「借主を守るための特別ルール」として
借地借家法が作られているんです。
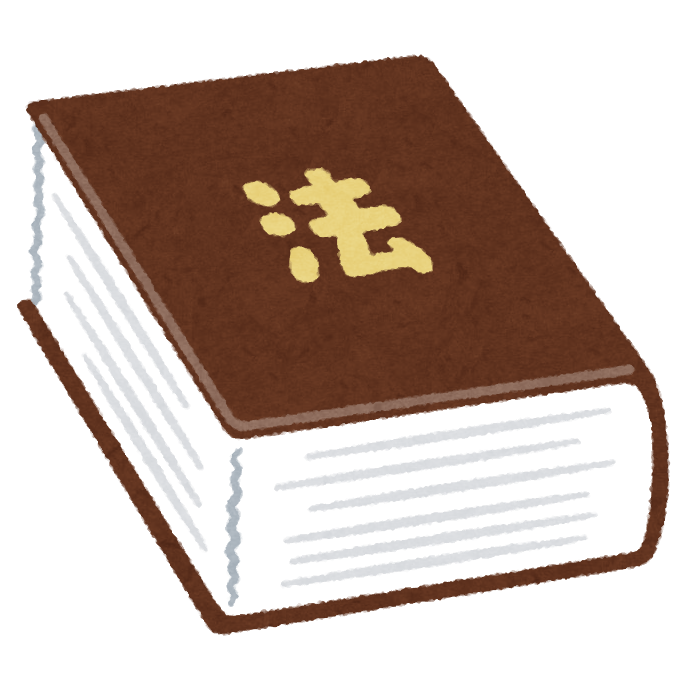
つまり、こういう構造になっています:
- 民法:契約の基本ルール(一般法)
- 借地借家法:賃借人保護が主な特別ルール(特別法)
なので、原則として
「土地や建物の賃貸借には
借地借家法が優先される」
と覚えてOKです。
ただし、
すべての賃貸借に借地借家法が
適用されるわけではありません。
たとえば…
- 借りてるのが居住用じゃない建物
(例:倉庫、短期テナント) - 契約の形が“使用貸借”
(=タダで貸してる) - 契約の対象が「動産」や
「車庫スペース」など
建物そのものでない場合

こういったケースでは
借地借家法は適用されず、
民法のルールが使われます。
また、同じ建物の貸し借りでも
「定期借家契約」など
特別な契約形式を結んでいる場合は、
普通借家契約とはまったく違う
ルールになるため要注意!
試験ではこうした「適用される法律の区別」を
ちょっとだけズラして出してくるので、
「民法 vs 借地借家法」の
境界線をしっかり理解しておくことが重要です。
まとめ: 借地借家法は“数字と整理”がカギ!得点源に変えよう!
借地借家法は、
数字暗記と状況の整理さえできれば
“確実に点が取れる”
おいしい分野です!
覚える数字の量や、
民法との比較する問題が
多いので苦手意識を持つ人は
多いと思いますが
過去問や比較表、図解などを活用しながら
少しずつ理解を深めていけば、
「なんだ、意外と簡単に得点できるじゃん!」
と思える瞬間が必ず来ます!

そして、宅建試験では
ほぼ毎年「借地」と「借家」の
それぞれ1問ずつ出題される超・重要分野。
この2点をしっかり取れるかどうかが、
合否を分けることもあるんです。
だからこそ、あきらめないでほしい。
まずは、
「普通借地=30年以上」「普通借家=原則期間なし」
などを暗記カードに書いてみたりして、
ひとつずつ覚えるところからでOK
焦らず、一歩ずつ。
数字の意味が少しわかるようになった、
過去問で1問解けた、
それだけであなたは確実に前に進んでいます。
今日の学びが、明日の自信になります。
一緒に、乗り越えていきましょう!

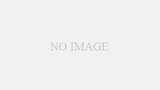
コメント