こんにちは!
宅建士兼エンジニアのアジサイです!
突然ですが、宅建士試験の勉強をしていて
「民法の分野が難しい…」
「条文を読んでも、
頭に入ってこない…」
「なんか、読めば読むほど不安になる…」
その悩み、
痛いほど分かります。
私自身、
勉強を始めたばかりの頃は
民法の問題文を見るたびに、
「え、これ…何語?」
と感じていました。
でも、
ある“読み方のコツ”
を知ってから、
あれほど意味不明だった条文が、
噓のように読めるようになったんです!
しかもそれは、
特別なスキルが
必要なわけではなく、
「ある視点」さえ持てば
誰でもできる方法なんです。

民法のコツを知らないと、こうなってしまうかも…
民法は14問ある権利関係の大部分を
占めています。
つまり、
試験の3割近くを占める権利関係の
超重要パートです。
この読み方のコツを知らずに突っ込んでしまうと…
- 文章が長すぎて意味がつかめない
- 誰が誰に何をしたのか、全く整理できない
- 結局「なんとなくの勘」で選ぶことに…
こんな状態になってしまい、
民法を「ほぼ捨てるしかない…」
という受験生も少なくありません。
でも逆に、
「民法は物語として読む」
「民法は物語として読む」
条文や判例がまるで
ドラマのセリフのように
頭にスッと入るように
なるんです!
この読み方を知っておくと、合格がグッと近づく!
実は民法は、
人と人が、何かをして、
どういうトラブルが起きたのか?
という“人間関係のやりとり”
を扱っているだけ。
つまり、
読み方さえ変えれば、
内容そのものは意外と
複雑じゃないんです
民法を苦手科目にする人が多い今こそ、
あなただけがこの“読み方のコツ”
をマスターできれば、
ライバルに差をつける
大チャンスです!
この記事を読むと、こんな未来が待っています
- 意味不明だった条文の
“読み方”がわかるようになる - 「誰が何をしたのか?」
が整理でき選択肢の正誤判断がしやすくなる - 民法を“苦手科目”から
“得点源”に変えるヒントが手に入る
そもそも民法とは
一言でいえば…
人と人との権利・義務のルール
を定めた法律です。
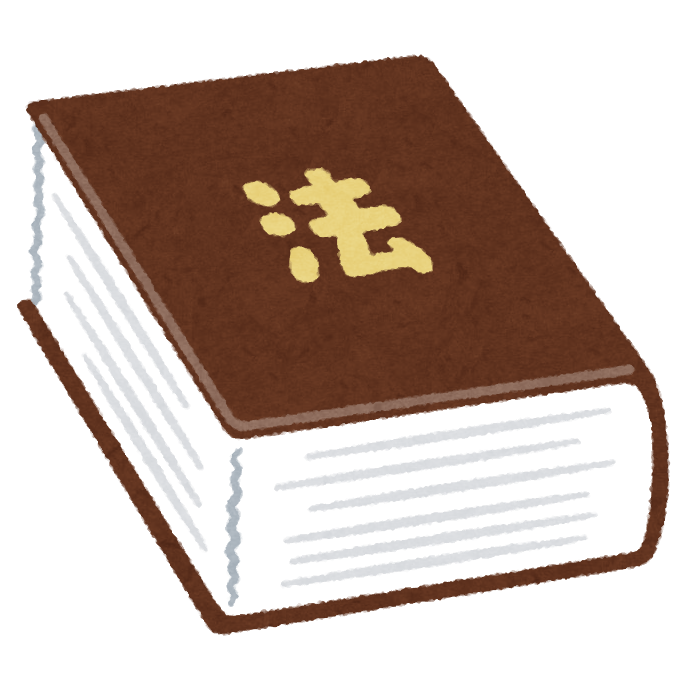
例えば──
・誰かにお金を貸したのに返してもらえない
・隣人との土地の境界でもめた
・お店で買った商品が壊れていた
・親が亡くなって相続の話になった
こういった
日常のトラブルや
契約ごとに関わるルールが、
すべて民法に書かれています。
宅建士試験では「権利関係」と
呼ばれる科目で、
主にこの民法の基礎を問われます。
宅建士の仕事では不動産売買や
賃貸契約など「人と人との約束」が関わるため、
民法の知識がとても大事になるのです。
民法が難しく感じる理由とは?
民法の説明を
ざっとお話ししましたが、
民法の勉強を始めたばかりの
受験生がまずぶつかるのが──
「文章が硬すぎて何を言ってるか
分からない……」
「誰が誰に何をしたのか、
頭の中で整理できない……」
まるで
“国語の長文読解”の難問を
解かされているような
気分になりますよね…
自分も活字が苦手なので
本当に条文を見るのが嫌でした…
実際の問題で例を挙げると
実際の宅建試験では
こんな問題が出てきます
A所有の甲土地につき、Aから売却に関する代理権を与えられていないBが、Aの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、表見代理は成立しないものとする。
1.Bの無権代理行為をAが追認した場合には、AC間の売買契約は有効となる。
2.Aの死亡により、BがAの唯一の相続人として相続した場合、Bは、Aの追認拒絶権を相続するので、自らの無権代理行為の追認を拒絶することができる。
3.Bの死亡により、AがBの唯一の相続人として相続した場合、AがBの無権代理行為の追認を拒絶しても信義則には反せず、AC間の売買契約が当然に有効になるわけではない。
4.Aの死亡により、BがDとともにAを相続した場合、DがBの無権代理行為を追認しない限り、Bの相続分に相当する部分においても、AC間の売買契約が当然に有効になるわけではない。
出典:平成24年度 宅地建物取引士試験問4
……読んでみて、
どう感じましたか?
「え、誰が誰に何をしたの?」
「AとBとCとDって、
何の話?追認?無権代理?え?」
と混乱する方も多いと思います。
これはあなたの理解力が低いわけでも、
読解力が低いわけでもありません。
原因はただひとつ。
民法の文章が
“人間の出来事”を、
めちゃくちゃまわりくどく
書いている
からなんです。
民法は“読み方”で変わる:理解できない人の共通点
民法が難しいと
感じてしまう人に共通するのが、、
条文や問題文を「文字」として
そのまま読もうとしている
ということ。
でも、実は民法の内容って……
- 誰かが誰かと契約したり
- 誰かが勝手に契約して怒られたり
- 誰かが亡くなって相続が発生したり
そんな“人と人とのストーリー”なんです。
BがAに無断で
「Aの代理人だよ〜」と勝手に
土地を売ってしまった。
さて、それをあとからAが
OKするのか?しないのか?
さらに相続が絡んできたら、
話はどうなるのか?
といった
「ちょっと複雑なドラマ」なんです。

そう考えると、
少し親近感がわいてきませんか?
登場人物の関係性や
出来事の順序を、
物語のように
整理していくと、
一見、複雑に見えた条文も
“なるほど”と
腑に落ちるようになります。
では、
どうすれば民法の条文を
ストーリーとして理解できるのか?
次の章では、
条文読解が“スッと”ラクになる
読み方のコツを紹介していきます!
読み方のコツは“登場人物と関係性”
民法を読むとき、
最初に意識すべきは
以下の2つです:
- 登場人物は誰か?(A・B・Cなど)
- 誰が、誰に、何をしたのか?
これだけで、
頭の中で物語が
整理できて、
「ああ、なるほど。そういうことか!」
と“スッと腑に落ちる
”瞬間が増えていきます。
民法は「法律」ではありますが、
解きほぐしていくと
“人間関係の物語”です。
上の問題を例にこの2ステップを実践してみましょう。
それぞれの立場を整理する
まず、
問題に登場する人物と
立場・前提を表でまとめてみます。
| 人物 | 立場 | できごと・前提 |
|---|---|---|
| A | 土地(甲)の本当の持ち主 | 土地の売却を考えていない |
| B | Aの子供。代理権を持っていない | 勝手にAの代理人として売却 |
| C | Bと契約を結んだ買主 | Aに直接関係はない |
| D | Aが死亡後の相続人の1人(4番で登場) | – |
いつ・誰が・何をしたかを順序を時系列で追う
それでは選択肢ごとに、
誰が何をしたのかを
物語のように追ってみましょう。
選択肢1
AがBの無権代理を追認した
Aが「勝手に売ったのはいいよ」
と認めたので、契約は有効。
→ 正しい
選択肢2
Aが死亡→BがAを相続→Bは追認を拒否
BがCに対して「やっぱ売りません」と言った
自分で勝手に売っておいて、
あとから「やっぱダメ」と
言うのはダメ!
→誤り
選択肢3
Bが死亡→AがBを相続→Aは追認を拒否した
契約を勝手にしたBが死亡、それをAが引き継いだけど“やっぱ追認しない”と拒否した
これはOK。
契約を勝手にしたBが亡くなって、
Aがそれを相続したが、
「追認しない」と判断。
これは法律上OK。
信義則違反ではない。
→ 正しい
選択肢4
Aが死亡→BとDが共同で相続→Dは追認してない
追認は全員一致で必要。
Dが追認しなければ、
その分の契約は有効にならない。
→ 正しい
よって、誤っているのは選択肢2
ストーリーで考えると、民法は“わかる科目”になる!
いかがでしょう?
このように、
人物の関係と流れをストーリーとして
整理するだけで、
「誰が何をしたのか」
「どう判断されるのか」
がグッと理解しやすくなります。
民法の条文や問題文は
“難しく見せてるだけ”。
実は人間関係と行動の整理で
ちゃんと解けるようになります!
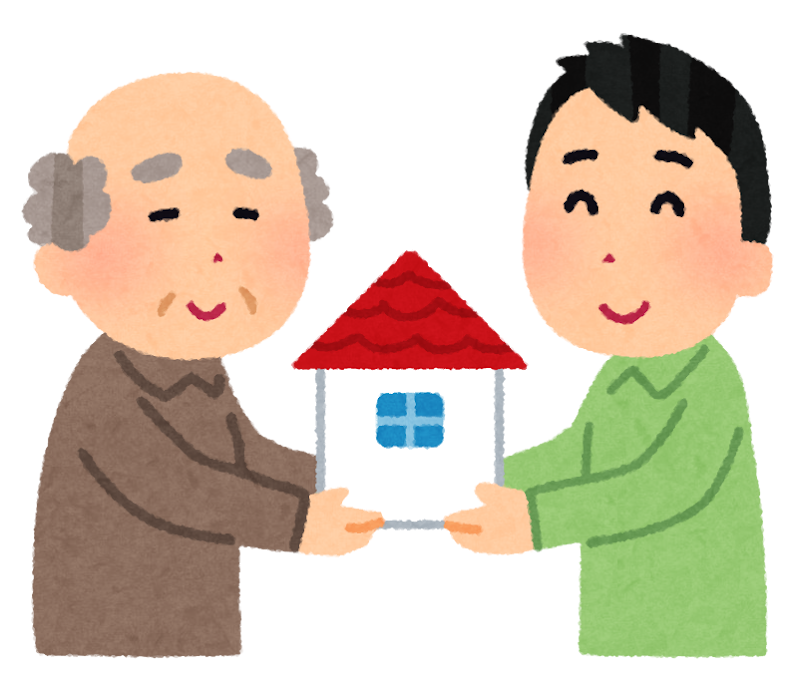
まとめ:民法は“読解力”ではなく“読み方のコツ”で攻略
民法を難しく感じる最大の原因は、
内容そのものの複雑さ
ではなく、
法律独特の回りくどい書き方
にあります。
でも実は、
民法の多くの条文や問題は、
誰が、誰に、
何をして、どうなったか?
こうしたシンプルな構造です:
つまり、
人間関係と行動の流れを
物語のように捉えれば、
あの難解な文章も、
グッと理解しやすくなるんです!
これからの勉強で意識すべき3つのポイント
登場人物を整理する
名前(A・B・Cなど)に
〇をつけてメモする
誰が、誰に、何をしたか?を時系列で追う
関係性を矢印などで
つなぐとスッキリ!
条文を「人間ドラマ」として読む習慣をつける
物語として読むことで、
記憶にも定着しやすくなります!

最初は、
1日1問でもOK。
登場人物と行動の整理から
始めてみてください!
数ヶ月後にはきっと、
「民法=苦手科目」ではなく、
「民法=点が取れる得意分野」
に変わっているはずです!
この小さな読み方の意識改革が、
宅建合格の大きなカギになりますよ!

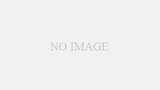
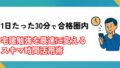
コメント