こんにちは!
宅建士兼エンジニアのしゅんです!
突然ですが、
「宅建の勉強を始めよう!」
と意気込んで、
本屋やネットを覗いてみたものの…
棚にずらっと並んだ参考書の数に圧倒されて、
「結局、どれ選べばいいの?」
と立ち尽くしていませんか?
その迷い、めちゃくちゃわかります…
というのも、
宅建の参考書や講座は
本当に種類が多くて、
初学者こそ「何を基準に選べばいいのか」
がわからなくなるからです。
でも、そんなあなたに最初に伝えたいのは──
全部読む必要なんて、
ありません!
図解が豊富な“1冊”を
選ぶだけで十分です!
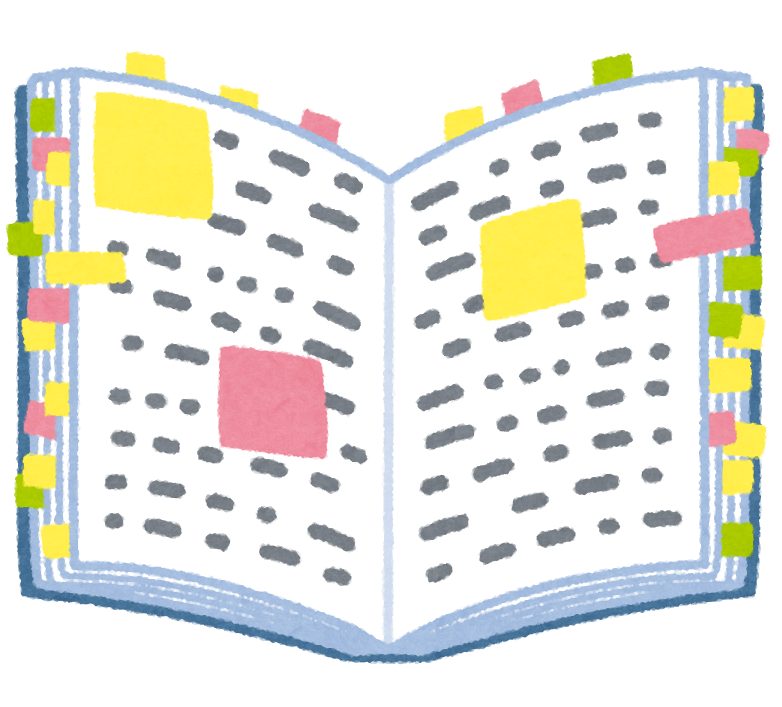
なぜなら宅建の学習内容は、
法律用語・民法の条文・数字やルールなど、
「言葉だけではイメージしづらいもの」
ばかりだからです。
逆に、この視点を知らずに
参考書を選んでしまうと…
文字びっしりの難解な
テキストに手を出して、
内容が全然頭に入ってこない
その結果…
- ページが進まず、モチベーションが下がる
- 結局、テキストを読まなくなって
試験勉強がストップ…
という最悪のパターンに
ハマってしまう危険もあります…
だからこそ今回は、
初心者が“迷わず選べる
宅建テキストの選び方”
について、
図解を活用した効果的な勉強スタイル
とともに解説していきます!
なぜ初心者ほど“図解の多いテキスト”を選ぶべきなのか?
宅建の勉強を
始めたばかりの人にとって
一番のハードルは──
言葉だけだとイメージがわかない

という壁です。
たとえば、都市計画法に出てくる
「市街化区域」「調整区域」「非線引き区域」や、
建築基準法の
「建ぺい率」「容積率」といった用語。
文字で説明されても、
「結局どういう土地で、何が建てられるの?」
というイメージが頭に浮かびにくいのが実情です。
民法の条文は特に顕著で
民法第95条より引用
- 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
- 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
- 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
「え、何?日本語でOK」
なんて思ってしまいます…
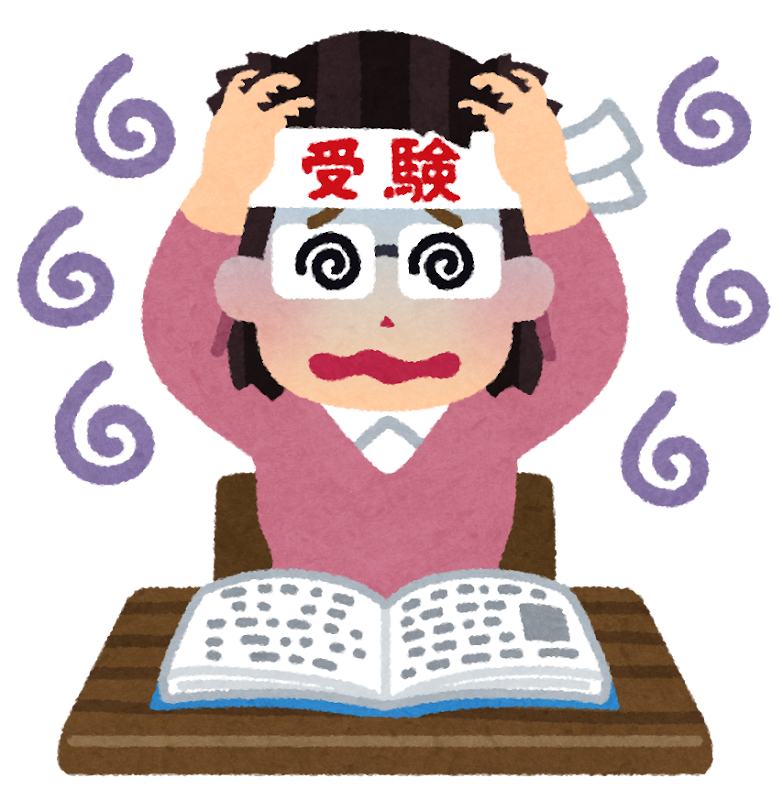
実際、私自身も勉強を始めた当初、
こんな民法の条文を読んでは
「で、どういう意味?」と毎回手が止まり、
進めば進むほどモヤモヤが
積み重なっていきました。
でも、その状況を変えてくれたのが
図解メインのテキストでした。
詐欺の構図や、意思表示の流れを
「登場人物の図」や「矢印つきのフローチャート」
で整理してくれる教材に出会ってからは、
- 誰が詐欺をしたのか
- その相手は誰だったのか
- 第三者が関わっているかどうか
といった人物関係がパッと可視化され、
イメージがどんどん湧くようになったんです。
こちらの記事でも書いていますが、
民法は人と人との関係を表現した
人間ドラマです。

文字だけではその関係性を
イメージするのがとても難しい。
だからこそ、最初に選ぶ教材こそ、
図解多めのテキストが圧倒的におすすめなんです。
言葉→理解
という順番ではなく、
図→理解→言葉
という順で学ぶと
民法もグッと読みやすくなります!
図で理解するメリット:民法・法令・数字がスッと頭に入る!
宅建の試験勉強で図解なしで
覚えることが困難な代表格が、
民法、法令上の制限、
そして数字が絡む暗記事項です。
どれも文章が抽象的だったり、
数字のパターンが複雑だったりして、
文字だけを読んで覚えようとすると、
どうしても“拒絶反応”が出てしまいます。

そんなときに圧倒的な威力を
発揮するのが「図解」
たとえば民法でよく出てくる「代理」のルールも、
登場人物(本人・代理人・相手方)を
線や矢印で関係図にしただけで、
条文の意味が一気にクリアになります。
さらに──
- 用途地域の種類と建てられる建物の関係表
- 開発許可が必要な区域のフロー
- 建ぺい率・容積率の計算パターン
こういった
「条件が分岐するテーマ」や
「数字が絡むルール」も、
図にまとめることで、
文字では見えなかった関係性が“見える化”されます。
一度イメージで理解できた内容は、
単なる暗記ではなく
“体感としての記憶”になるので、
試験本番で選択肢に迷ったときの
判断力にも直結します。
だからこそ、
民法・法令・数字問題に苦手意識がある人ほど、
図解は必須ツール。

と言えるでしょう
宅建テキスト選びでよくある失敗とは?
ところで、勉強を始める際…
「この参考書も良さそう」
「あっちの解説の方が分かりやすいかも…」と、
つい何冊もテキストを買い集めてしまうこと、
ありませんか?
実はこれは…
初心者が最初にハマりがちな“落とし穴”
なんです…
たしかに、
どのテキストにも良さがあります。
でも、それぞれの書き方や図の使い方、
用語の覚え方などが微妙に違うため
同じテーマを読んでいるのに、
「この本ではこう書いてあるけど、
あっちの本では違うような…?」
と混乱してしまうことが多いんです。
だからこそ初心者には、
「1冊(または同じシリーズ)に絞って、何周も繰り返す」
という勉強法が、最も効率的でおすすめです!
テキストが統一されていれば、
出てくる言い回しや
図解も一貫しているので、
理解のスピードも
記憶の定着もぐっと上がります。
宅建は情報の多さではなく、
「理解と定着」が勝負の試験。

まずは1冊だけに絞って、
そのテキストと“言語を合わせる”意識で
読み込んでいきましょう!
まとめ: 迷ったら「図解でわかる1冊」から始めよう!
宅建の勉強を始めたばかりのとき、
「どの参考書が自分に合っているか?」なんて、
正直わかりませんよね。
かく言う私も、
最初の頃はどのテキストも
それぞれ魅力があり、
どれがあってるかわかりませんでした…
未経験にとって宅建士試験の内容は、
呪文のような言葉が書かれた
魔導書のようなもの…
だからこそ大事なのは、
最初の1冊を“完璧に読み切れるかどうか”
で選ぶことです!

その中でも、
初心者がもっとも挫折しづらいのが
図解が豊富でイメージしやすいテキスト。
図があるだけで、
民法の人間関係や、法令の構造、
数字の計算ルールなどがスッと頭に入り、
「わからない」から「なんか理解できるかも」
へと意識が変わります。
そして、1冊を何周も読み込んでいくうちに、
用語の意味、条文の背景、計算の感覚が
自分の中にしみ込んでいきます。
逆に、あれこれ手を出してしまうと、
本ごとの表現の違いに混乱して、
インプット効率が落ちてしまうことも…。
ですから、参考書選びで迷ったら、
まずは“図で理解できる一冊”を
手に取ってみてください。
あなたにとって
“読み進められること”こそが、
最初の大きな成功体験になります!
本屋やAmazonで
「図解 宅建」「イラストでわかる宅建」などで検索してみる
宅建合格への一歩は、
「見てわかる」ことから
始まりますよ!

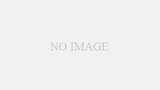
コメント