こんにちは!
宅建士兼エンジニアのしゅんです!
突然ですが、
過去問を解いていて…
「えっ、なんでこれ間違ってるの?」
「正しいと思ったのに…またひっかかった…」
「結局、問題文の読み違いばっかりで点が取れない…」
こんな経験、ありませんか?
その気持ち、めちゃくちゃ分かります…
実は、私も宅建の勉強を始めたばかりの頃、
“知識不足”ではなく“ひっかけ”にばかり
引っかかってしまい、
何度も同じような間違いを繰り返していました。
特に宅建業法では、
「相手が業者か一般か」「媒介か代理か」
「条文の語尾が微妙に違うだけ」
など、
ちょっとした文言の差で、
正解と不正解が分かれてしまう
ひっかけ問題が満載なんです。

でも、それに気づいてからは、
- 「問題文を丁寧に読む」
- 「設問のパターンに慣れる」
- 「ひっかけ傾向を分析する」
これらを徹底したことで、
安定して点数が伸び、
特に宅建業法では
ほぼ満点近くを取れるようになりました!
宅建業法はぜひとも満点を目指したい分野ですので、
ひっかけ問題で点数を落とすのは
もったいないです。
逆にひっかけ問題さえ克服できれば、
宅建業法は安定した得点源になり果てます!
でも、この記事を読まないと――
- 「ちゃんと覚えたのに、なぜか点が取れない…」
- 「毎回“ひっかけ”にやられて、ケアレスミスで失点…」
- 「実力があるはずなのに、本試験で合格点に届かず不合格…」
そんな“もったいない未来”が
現実になってしまうかもしれません。
ひっかけ対策は、点数を上げる伸びしろです!
この記事を読めば、こんな未来が待っています。
- 問題文のひっかけポイントが一瞬で見抜けるようになる
- 本試験で落ち着いて問題を読み、正解を積み重ねられる
もう迷わない!ひっかけ問題の典型パターンと読み方
宅建試験では、
「一見正しそうに見えるけど実は間違っている」
そんな巧妙なひっかけ問題が
毎年必ず出題されます。
実際の問題例
例えば、こんな問題。
Aさんが所有している土地を5区画に分けて、
複数人に貸し出そうとしている。
この行為は宅地建物取引業に該当するか?
あなたはどう思いましたか?
一見、
「複数に貸すなら業として行っているんじゃ?」
と思いがちですが
答えは「該当しない」です。
この問題は、
「自ら貸す」行為は宅建業に該当しないという
基本原則を知らないと、
見事に引っかかってしまいます。

押さえておきたいポイント
宅建業法では、
以下のように区別されています。
| 行為 | 宅建業の対象か | 免許の必要性 |
|---|---|---|
| 自ら売る・自ら貸す | 対象外(自ら貸す場合) | 不要 |
| 代理する・媒介する | 対象 | 必要 |
つまり――
- 自分が所有している土地を貸す
→ 免許不要 - 他人の所有地の貸し借りを代理・仲介する
→ 免許必要

今回の場合、
このルールを正確に理解していないと、
「分けて貸す=商売してる=宅建業にあたる」
と勘違いして不正解になります。
要注意な“単位ズレ”のひっかけ問題
宅建の問題では、「以上・超」「未満・以下」といった
数値の比較表現でも多くの受験生が引っかかります。
例えば、こんなケース
「延べ面積が200㎡“超”の建築物は~」
というルールがある場合、
「200㎡ぴったり」の建物は対象になる?
答えはならないです。
なぜなら、この場合「超」は200.01㎡からを指すから。
用語の違いを正しく理解しよう!
この違いは本試験での引っかけの定番中の定番。
私も勉強初期の頃、過去問で
何度も「以上」と「超」を読み違えて失点しました。
| 用語 | その数値が含まれるか? | 例:200㎡の場合 |
|---|---|---|
| 以上 | 含まれる | 含まれる(≧200) |
| 超 | 含まれない | 含まれない(>200) |
| 以下 | 含まれる | 含まれる(≦200) |
| 未満 | 含まれない | 含まれない(<200) |
宅建のひっかけ問題は、
- 言葉の意味の取り違え(以上・超 など)
- 条件のズレ(誰が?いつ?いくらで?)
- 例外の見落とし(“ただし”以降を見逃す)
によって作られることが多いです。
読み飛ばさず、“1文字の違い”まで意識すること!
本試験では、時間の焦りや緊張感が重なり、
平常時では引っかからないような問題にでも足を取られがちです。
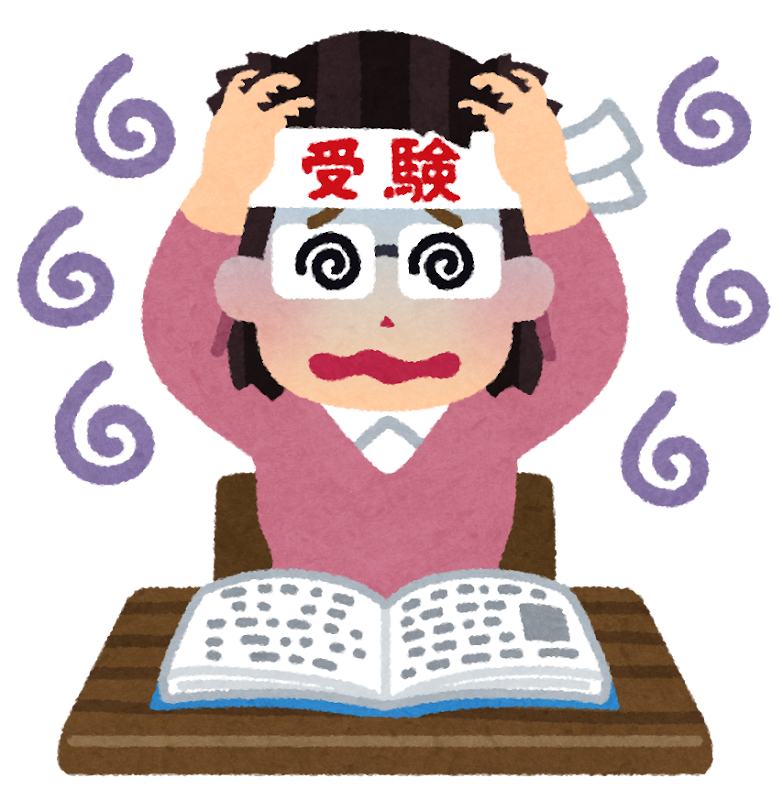
だからこそ大切なのは…
- 選択肢を丁寧に読む
- 数値や単語はマーカーや印で強調する
- 選択肢の“条件”に注目する
こういった“読む力”と“見る視点”が、
あなたのひっかけ耐性をグッと高めてくれます。
引っかからないための“読解思考法”
宅建試験は、法律をベースとした
“用語の精密さ”が問われる国家資格試験です。
そのため、
「1文字の違い」が命取りになるひっかけ問題が、
毎年必ず出題されます。
ここからは実際に自分も実践した
3STEPをご紹介いたします
STEP1:まずは“精読”を習慣化しよう:マーカー読解法
受験者の多くが実践しているのが、
「問題文に線を引く」「数字や条件にマークする」
といったものです

例えば、
「延べ面積が200㎡超の建物」
という選択肢を見たときに、
「超」→ 200㎡は含まれない
と“瞬時に読み取れる”ようにしましょう
ここがポイント
- 「以上/超」「以下/未満」は線を引いて印象づける
- 数字、期限、条件はマーカーで強調する
STEP2:過去問でよくあるひっかけパターンになれよう!
実際の試験では、
過去問に近いパターンでのひっかけ問題
が多く出題されています。

だからこそ――
ひたすら過去問を繰り返して
ひっかけ問題になれよう!
とくに、過去問を通してみて、
間違えた問題がひっかけ問題だった場合
間違えたひっかけ問題集を
作ってみるといいと思います
STEP3:模試形式で読む習慣をつけよう!緊張感が理解力を鍛える
どれだけ読み方を覚えても、
本番では緊張と焦りで読み間違える可能性が高くなります。
その対策としておすすめなのが、
時間を測って模試形式で問題を解くこと。
本番と同じスピード感で読む練習をすることで、
実際の試験でも“1文字の違い”を
見逃さない力が自然と身につきます。

まとめ:読み方次第でひっかけから脱却できる!
宅建試験で点数が伸び悩む
最大の理由のひとつが「ひっかけ問題」。
でも、それはあなたの知識が
足りないわけではありません。
ほんの1文字の読み違い、
文中の“例外条件”の見落とし、
思い込みによる早とちり。
こうした「読解のクセ」が
原因になっていることが大半なんです。
そして裏を返せば――
“読み方”を少し工夫するだけで、
ミスは確実に減らせます。

たとえば…
- 「超」「以上」「未満」「以下」の違いを意識して読む
- 問題文の中の主語(誰が)・動詞(何を)を丁寧にチェックする
- 過去問でひっかかった問題を「ひっかけ集」としてまとめる
- マーカーで数字や条件を強調し、集中力を切らさない工夫をする
このような“読解思考の型”を身につけることで、
「正しいはずなのに間違えた…」
という悔しさは確実に減っていきます。
知識があっても、読み違えれば不正解。
逆に、知識があやふやでも、
しっかり読めば正解できる問題もあります。

まずは、ネット上で
「宅建 ひっかけ問題」
などで調べてみるだけでもOKです!
だからこそ今すぐ意識してほしいのは、
読解力は、
宅建の得点を左右する
最強の武器になる
試験本番で焦らず、落ち着いて、
正確に選べるように。
今日から少しずつ、
「読む力」を鍛えていきましょう!
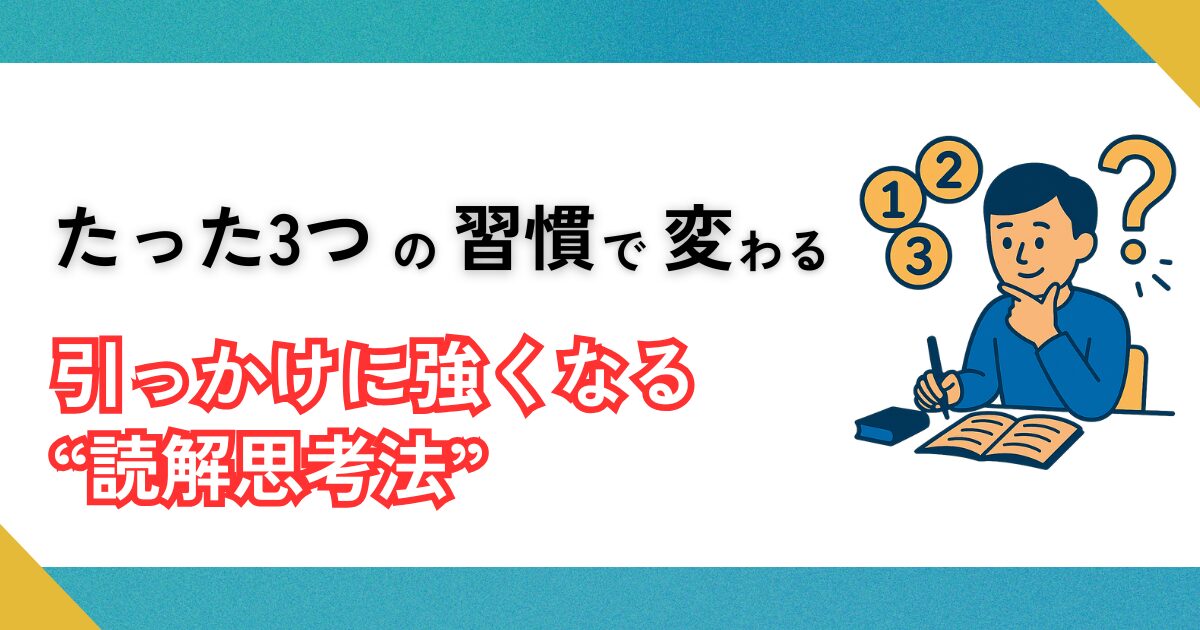
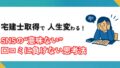

コメント