こんにちは!
宅建士兼エンジニアのしゅんです!
突然ですが、
独学で宅建士を目指したいけど、
どこから手をつけていいか
わからない…
効率よく勉強したいけど、
注力すべきテーマが
見えなくて不安…
そういった悩みを抱えている、
そこのあなた…
安心してください。
私もまったく同じ
気持ちからスタートしました…
当時の私は――
- 不動産業界の経験なし
- 法律の知識ゼロ
- 他の資格も持っていない
- お金も時間もかけられない
そんな状態から、
半年間の独学だけで
宅建士試験に一発合格しました!
結論から言えば――
宅建士は難易度も
難関とされていますが、
「戦略的に学習すれば」
未経験・独学でも
半年で十分に合格が可能な資格です!

宅建士は“コスパ最強”の国家資格!
宅建士資格は、
たとえ学歴や職歴に自信がなくても、
就職・転職の強力な武器になります。
さらに、
企業によっては「宅建手当」として
月1〜3万円の手当がつくこと
も珍しくありません。
つまり、
合格すれば一気に
「選ばれる側」に
変わるチャンスなんです。
ただし、やみくもに勉強するのはNG!
とはいえ、
何の計画もなく勉強を
始めてしまうと――
- 分厚いテキストに手を出して、途中で挫折
- 必要以上に時間がかかって、やる気が失速
- 勉強してるのに点が伸びず、自信喪失
…なんてことに
宅建試験は
年に1回
しかチャンスがありません。
落ちてしまえば、
もう1年やり直しです。
だからこそ「学習の優先順位」が命!
重要なのは、
「何を捨てて、何に集中するか」を
最初に明確にすること。
実際に私自身も、
宅建業法から徹底的に攻めて、
合格に必要な点数を安定して
取ることができました
この記事では、
宅建未経験者でも
半年で合格を勝ち取るための
戦略的な学習ステップと
優先順位の決め方
を、わかりやすく丁寧に解説していきます。
「最初の一歩が踏み出せない…」
という方は、
ぜひこの記事を
最後まで読んでください。
あなたの半年後の
“合格”と“キャリアアップ”
に繋がるはずです!
この記事を読むと、こんな未来が待っています
- 半年・独学でも宅建合格を目指せる
「具体的な道筋」がわかる - 勉強の優先順位が明確になり、
ムダな遠回りをしなくなる - 出題傾向をふまえた「得点戦略」
を自分で立てられるようになる - 自分に合った勉強法と
スケジュールの作り方がわかる - 「やってみよう」と思える
“確かな自信”と“最初の一歩”が踏み出せる
そもそも宅建試験ってどんな試験?
「宅建って聞いたことあるけど、
実際どんな試験なの?」
「範囲が広いって聞くけど、
何をどれだけ勉強すればいいの?」
そんな疑問を感じている方、
まず安心してください。
結論から言うと――
「宅建業法」と「権利関係(民法)」
の2分野だけで
全体の約7割を占めています。
特に、
宅建業法に集中すること
が合格への最短ルートなんです!

まずは
宅建士試験の全体像を
ざっくりつかんでおきましょう。
宅建士試験は、
全部で
【50問/マークシート方式】
の国家試験です。
合格点はその年によって
少し前後しますが、
おおよそ
【35点前後】(満点の70%前後)
がボーダーとされています。
出題される4つの分野と配点バランスは以下の通りです:
| 分野 | 内容 | 出題数(目安) | 配点比率 |
|---|---|---|---|
| 宅建業法 | 宅建業者のルール・義務・罰則など | 約20問 | 約40% |
| 権利関係(民法) | 契約、相続、代理、所有権など | 約14問 | 約28% |
| 法令上の制限 | 建築・都市計画・国土法など | 約8問 | 約16% |
| 税・その他 | 登記法、地価公示、税金など | 約8問 | 約16% |
ここがポイント
上の表からも分かるように、
- 「宅建業法」+「民法」で約7割
- 特に「宅建業法」だけで全体の4割!
しかもこの宅建業法、
内容のほとんどが暗記系で
構成されています。
つまり、
過去問を繰り返すだけで
得点が安定しやすいんです。
一方、
民法は文章が難しく、
理解にも時間がかかるため
苦手とする受験生が多数。
そこで重要なのが、
「出題数 × 得点しやすさ」= 勉強の優先順位
次章からは、
どの順番で勉強を進めると効率的なのかを
実際の体験も交えて解説していきます!
最初にやるべきは「全体像の把握」
宅建士試験を独学で
攻略するために、
まずやるべきこと。
それは――
「全体像」と「得点戦略」を
最初に明確にすること。
この段階をすっ飛ばしてしまうと、
時間も労力も
ムダにしてしまいます。
よくあるNGパターン
宅建の勉強を
始めたばかりの方の
多くがやってしまうのが、
まずはテキストを
最初からじっくり読もう
というパターン。
でも、これは
最短合格から最も遠い勉強法
なんです。
理由はシンプル
多くのテキストは
「権利関係(民法)」から
スタートする構成になっていますが、
民法は文章も概念も難解で
学習初期にいきなりやると挫折しやすいからです。
合格ラインは“満点じゃない”。だから戦略が重要
宅建士試験の合格点は
【50点満点中 約35点】
つまり、
満点を取る必要はなく
「確実に取れる得点源」
を先に押さえるべき
ということなんです。
たとえば、
「宅建業法」だけで
約20点(=全体の40%)
なので、
ここを満点近くまで取れれば、
他の分野で少し落としても
合格圏に届きます。
だからこそ、
いきなり民法に突っ込むより、
暗記中心で点が取りやすい
「宅建業法」から優先して攻めるのが
圧倒的に効率的なんです。

ありがちな失敗パターン
この戦略を知らずに、
- テキストを順番通りに最後まで読もうとする
- すべての分野を同じ熱量で勉強しようとする
といった勉強法を
取ってしまうと…
- 難しい民法でつまずく
- 得点源の業法にたどり着く前にモチベーションが下がる
- 「あと2点足りなかった…」と悔しい結果に
こんな残念な未来に
つながりかねません。
学習初期にこそ「全体像」が命
私自身、最初は民法から始めて、
意味不明な条文に
挫折しそうになったことがあります。
でも、
勉強の方針を切り替えて、
- 出題分野のバランスを知り
- 得点しやすい業法を最優先に押さえ
- 合格ラインから逆算したスケジュールを組む
という
3STEPの全体把握に
切り替えてから
一気に勉強が進みました。
最短ルートをつくる3つのSTEP
- 出題分野の比率と特徴を把握する
→「どこが出やすく、どこが取りやすいか」を知る - 宅建業法を最優先に押さえる
→ 20点満点が狙える得点源に集中! - 合格ライン(約35点)から逆算して勉強計画を立てる
→ 無駄を省いた効率重視の学習へ
この3ステップだけでも、
合格可能性はぐっと高まります。
宅建業法は最強の得点源!
宅建業法がなぜ最強の得点源なのか?
理由は明確です。
内容の大半が暗記系
民法のように
文章を読み込む必要がなく、
反復学習で点数が安定
出題テーマが固定されている
「免許制度」「35条書面」「37条書面」
「報酬」「重要事項説明」
など毎年よく出るテーマが明確
過去問と似た問題が本番にも出る
問題形式に慣れておけば、
試験中に“見覚えのある問題”が
並ぶ可能性も!
つまり、
得点効率 × 記憶定着 × 安定性
どの軸から見ても、
宅建業法は勝ちに行ける
科目なんです。
最初にやるなら、絶対ここ!
宅建業法を得意分野に
できるかどうかで、
合格の可能性は
大きく変わります。
「最初はどこから手をつければいいの?」
と迷ったら、
まずは宅建業法の章を開いて
1ページ読んでみる。
そこからすべてが動き出します。
まとめ:最初の一歩を迷わず踏み出そう!
宅建士試験は、範囲が広くて難しそう…
何から手をつければいいのか分からない…
そんな不安を感じるのは、
あなただけではありません。
でも安心してください。
大切なのは、
完璧な理解から始めることではなく、
正しい順序で動き出すことなんです。
合格のカギは「全体像の把握」と「得点戦略」
宅建士試験は全50問。
そのうち約7割は、
- 宅建業法(約20問)
- 民法(権利関係/約14問)
から出題されます。
このうち「宅建業法」は、
暗記中心で得点しやすく、
過去問と形式が
似ている出題が多いため、
最も得点効率が良く、
合格に直結する分野です。
たった半年でも、独学で合格できる理由
合格ラインは「50問中 約35点」。
つまり、
「満点」を狙う必要はなく、
得点しやすい部分に
集中して対策すれば
合格できる試験なんです。
チャンスは年に1度だけ。まずは動こう!
宅建士試験は、
年にたった1回しか
チャンスがない試験です。
「まだ準備が足りないかも…」
と悩んで何もしないよりも、
「まず宅建業法をちょっと読んでみよう」
と動き出した人の方が、
半年後の合格に
一歩も二歩も近づきます。
「何から始めたらいいかわからない…」
という方は、まず
テキストの目次や構成を
サラッと眺めて全体像をつかむ
だけでもOKです!
これだけで十分、
立派な第一歩です。
最初から完璧なスタートを
する必要はありません、
とにかく動き出すことが重要です!
一歩踏みだせば、
それだけで合格への道へ近づけます!
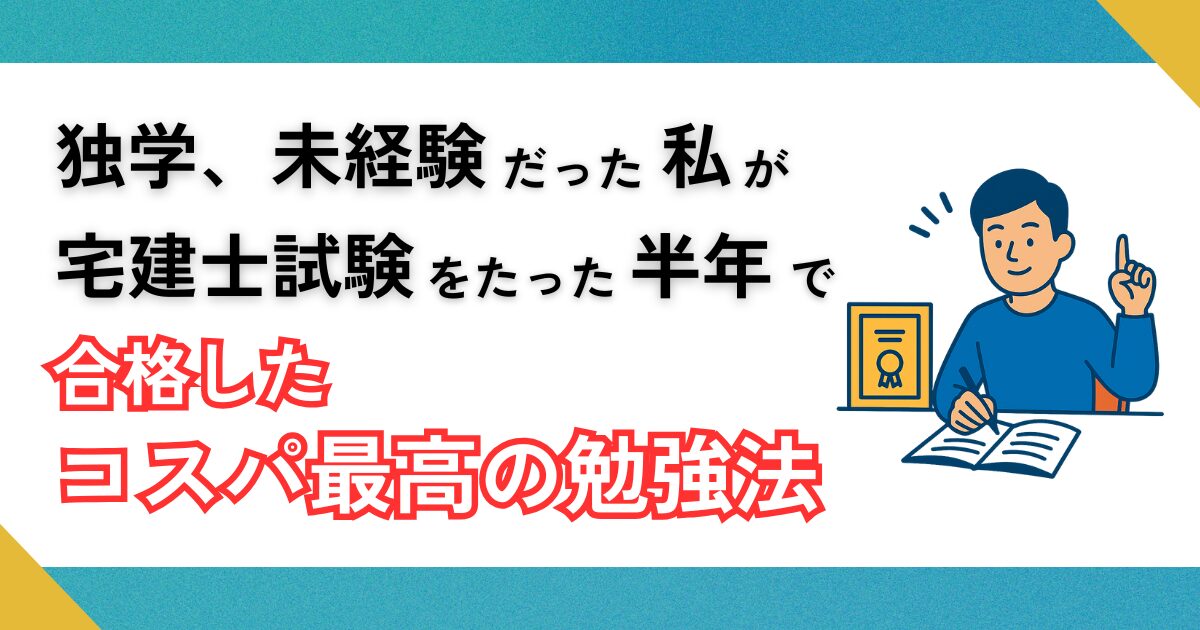
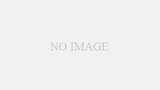
コメント